「電気工事士 やめとけ」。そんな言葉がネット検索で出てくるのを目にし、不安になった方も多いのではないでしょうか。これから電気工事士を目指す人、すでに現場で働いている人の中にも、「この仕事、本当に続けられるのかな」と思い悩む瞬間はあります。
確かに、電気工事の仕事は体力を要しますし、危険をともなう場面も少なくありません。現場ごとに異なる対応が求められ、思うようにいかないことも多いでしょう。そうした現実から、「きつい」「割に合わない」と感じた経験談が、ネット上にあふれているのも事実です。
けれども、それらの言葉だけを鵜呑みにするのは、少し立ち止まって考える必要があります。「やめとけ」と言っているのは、どんな立場の人なのか。どんな職場環境で、どんな働き方をしていたのか。そうした背景を知らずに受け取ってしまうと、本来は自分に合っているかもしれない仕事のチャンスを、自ら閉ざしてしまうことにもなりかねません。
電気工事士という仕事が、本当に誰にとっても「やめたほうがいい」のかどうか。それを見極めるためには、まずこの仕事の現実と魅力を、冷静に見つめ直すことが大切です。
たしかに「きつい」仕事。電気工事士が抱える現実とは?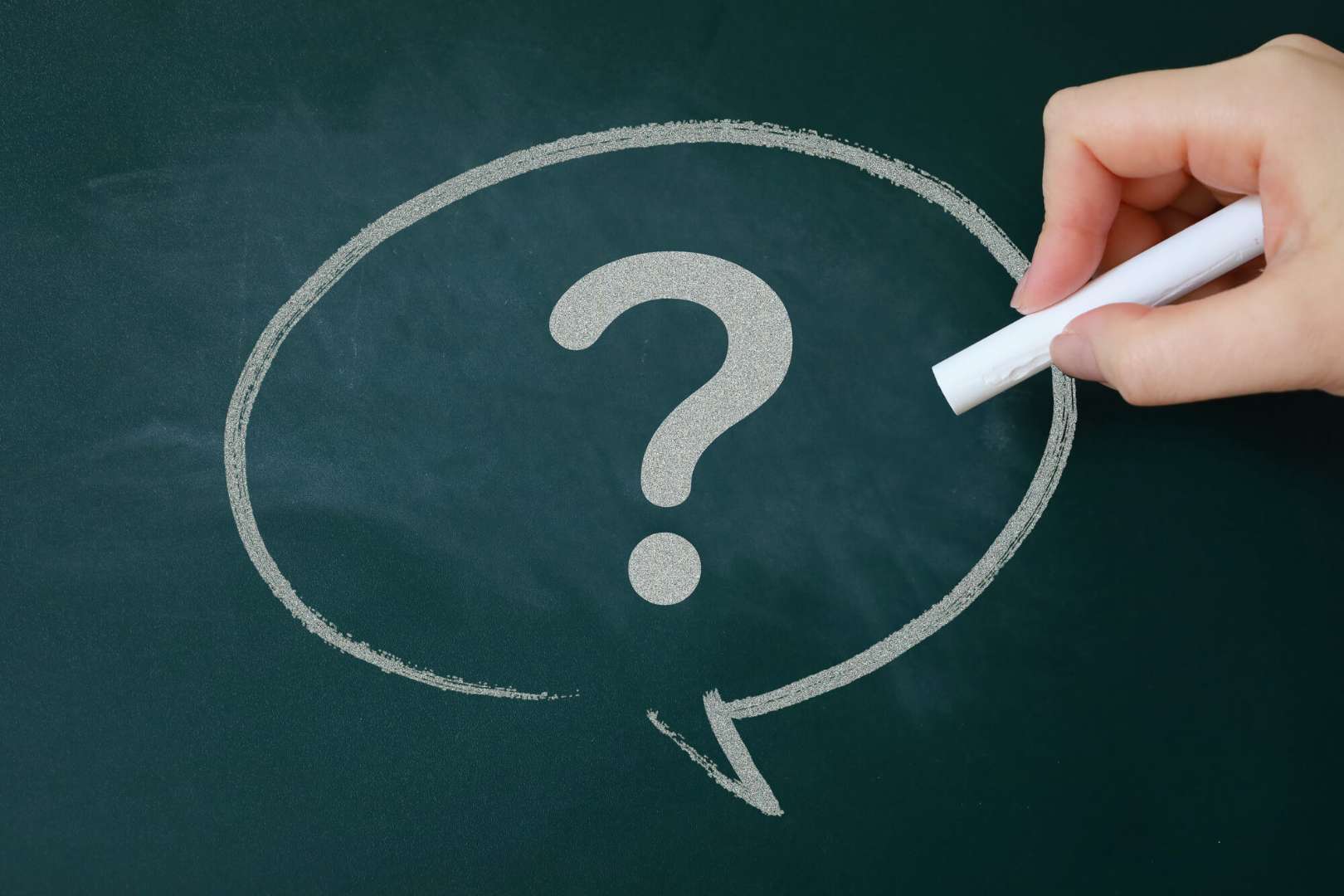
電気工事士の仕事が「やめとけ」と言われる理由のひとつに、労働環境の厳しさがあります。朝早くからの現場作業、炎天下や極寒の屋外での作業、重い工具の持ち運び、そして高所作業。こうした肉体的負担は、体力に自信のない人にとって大きなハードルになります。
さらに、作業の性質上「安全」が何よりも優先される職種であるため、常に緊張感を持って行動しなければなりません。一つのミスが事故やトラブルにつながる可能性があるため、慣れていても気を抜けないという精神的なプレッシャーも伴います。
もうひとつ、職場によっては新人への教育体制が整っておらず、「見て覚えろ」という風土が残っている現場もあります。そのような環境では、質問しにくかったり、孤立感を覚えたりすることもあり、特に未経験者にとってはつまずきやすい要因になり得ます。
また、労働時間や休日の取りやすさも、会社や現場によって大きく差があります。繁忙期には休日返上で働く必要がある現場もある一方、安定した勤務体系が整っている職場もあり、同じ「電気工事士」という職種でも実情はかなり幅があります。
これらの要素が重なり、「きつい」「辞めたい」という声が出てくるのは当然のことかもしれません。ただし、それは仕事そのものの問題ではなく、置かれている環境やサポート体制の影響が大きいケースも少なくありません。
それでも選ばれ続ける仕事には、理由がある
厳しい面がある一方で、電気工事士が「続けてよかった」と感じる人が多いのも事実です。まず挙げられるのが、社会に必要とされる職業であるという実感です。電気は、私たちの生活や産業に欠かせないインフラであり、その設備を安全に整備・維持する役割は、今後もなくなることはありません。
また、資格を持っていることで、一定の専門性と信頼性が得られるため、安定した仕事に就きやすいというのも強みです。経験を重ねれば、第一種電気工事士や施工管理技士といった上位資格を取得し、さらに収入や仕事の幅を広げることも可能です。資格がキャリアの土台になるという点で、長期的に見て価値の高い仕事と言えます。
「自分の手で作り上げたものが形として残る」という達成感も、多くの電気工事士が語る魅力のひとつです。建物や設備が完成し、そこに明かりが灯る瞬間には、大きなやりがいを感じられます。また、現場ごとに内容が変わるため、飽きずに働けるという声もあります。
さらに、経験を積めば独立・起業といった選択肢も見えてきます。努力が報酬や自由度につながりやすく、年齢に関係なくキャリアアップできる環境がある点も、この職業が多くの人に選ばれている理由のひとつです。
一見すると「大変そう」と思われがちな電気工事士の仕事ですが、その実、誇りと将来性を持てる職業であることは間違いありません。だからこそ、見かけのイメージだけで判断せず、自分に合った環境や進み方を丁寧に見極めることが大切です。
向き・不向きを知れば、ミスマッチは防げる
電気工事士の仕事が合うかどうかは、技術の習得よりも「どんな環境を選ぶか」と「自分の性格や志向に合っているか」に大きく左右されます。すべての人に適しているわけではありませんが、向き・不向きを知っておくことで、入職後のギャップを小さくすることは可能です。
たとえば、体を動かすことが好きで、細かい作業にも根気よく取り組める人は、現場作業にやりがいを感じやすい傾向があります。一方で、デスクワーク中心の働き方を望む人にとっては、最初の数年間は負担に感じる場面が多いかもしれません。
また、チームで動く現場が基本となるため、人とのコミュニケーションが苦にならないかどうかもポイントです。無口でも問題はありませんが、「報・連・相(ほうこく・れんらく・そうだん)」ができることは、安全面でも非常に重要です。加えて、天候や時間に左右される働き方に対して、柔軟に対応できる気持ちの余裕も求められます。
職場選びの観点では、未経験者の受け入れ体制が整っているかどうかが非常に重要です。「先輩が丁寧に教えてくれる」「資格取得を会社が支援してくれる」「休日や労働時間が明確に管理されている」といった環境があれば、未経験でもスムーズに仕事に慣れていけます。
逆に、こうした体制が整っていない会社では、早期に離職してしまうケースも珍しくありません。仕事そのものではなく、「働く環境」が合わなかったために辞めてしまう人が多いことを、もっと広く知られるべきかもしれません。
「自分に合っているか不安」と感じているなら、まずは見学や相談の機会を活用し、実際の働き方や職場の雰囲気を自分の目で確かめることが、最初の一歩になるでしょう。
▶ 採用情報はこちら
続けた人・辞めた人、それぞれのリアルな声
「やめとけ」と言う人もいれば、「続けてよかった」と語る人もいます。両方の声があるということは、それだけ電気工事士という仕事が、人によって感じ方が大きく分かれる職業であることを意味しています。
たとえば、早い段階で「自分には向いていない」と感じて辞めた人の中には、「体力的に想像以上にきつかった」「朝が早く、生活リズムが合わなかった」「先輩との関係がうまく築けなかった」などの理由を挙げることが多いです。こうした悩みは、特に新人のうちに集中しやすく、サポート体制の薄い職場ではなおさら顕著に現れます。
一方で、辞めずに続けた人の多くは、ある一定期間を乗り越える中で、仕事の面白さややりがいを見つけています。「最初はつらかったけど、電気が通ったときの達成感が忘れられなかった」「できる作業が増えるごとに、自分の成長を実感できた」「先輩に励まされながら、少しずつ自信が持てるようになった」といった声はよく聞かれます。
また、続けていくうちに、施工管理や設計、安全管理など、体力に依存しない分野にキャリアチェンジしている人もいます。現場経験を土台に、より安定的で計画的な働き方に移行できるのは、この職業ならではの魅力ともいえるでしょう。
大切なのは、辞めた人の理由も、続けた人の理由も、どちらも「自分にとってどうなのか」という視点で受け止めることです。他人の体験談を参考にするのは良いことですが、それが自分に当てはまるかどうかは、実際に経験し、見極めていく中で少しずつ明らかになります。
判断の軸は、他人の声ではなく「自分の視点」
インターネットには、「電気工事士はやめとけ」といったネガティブな意見があふれています。しかし、それらの声にすべてを委ねるのではなく、「自分にとってこの仕事はどうなのか」を見極めることが、後悔しないための第一歩です。
たしかに、電気工事士の仕事は簡単ではありません。体力も集中力も求められ、危険と隣り合わせの現場もあります。けれども、社会に欠かせない存在として人々の生活を支え続ける、やりがいのある仕事でもあります。そして何より、資格と経験が着実に自分の糧となり、未来の働き方を広げてくれる職業です。
この仕事を続けるか、やめるか。その判断を下すとき、他人の経験を材料にすることはあっても、最終的な判断はあなた自身が下すものです。大切なのは、「自分はどうなりたいのか」「どんな働き方をしたいのか」をしっかり見つめること。その問いに向き合うことで、選ぶべき道が見えてくるはずです。
少しでも迷いがあるなら、ひとりで抱え込まず、実際に現場で働く人の話を聞いてみることや、環境の整った職場を探すことから始めてみてはいかがでしょうか。
▶ ご相談はこちら


